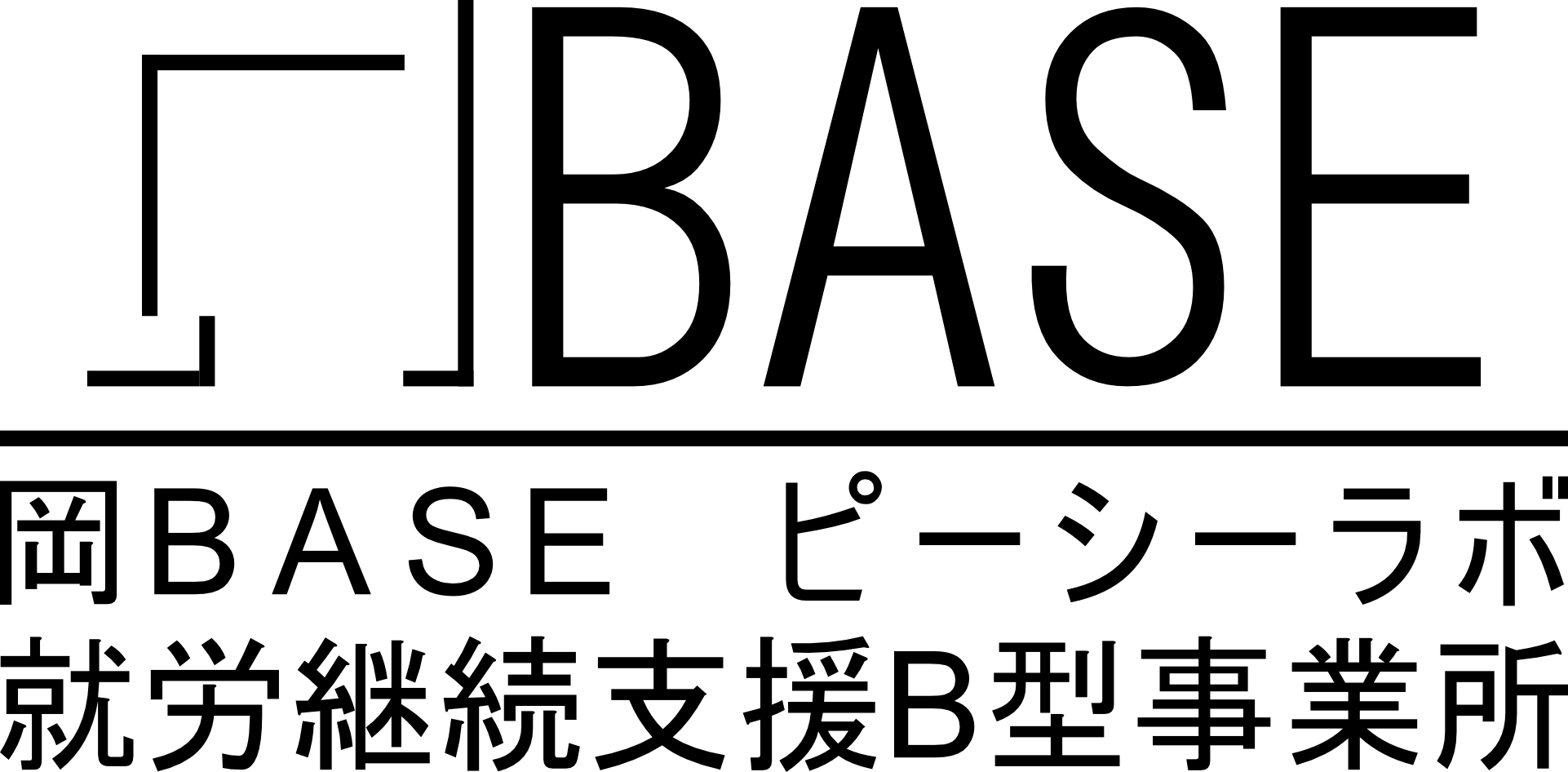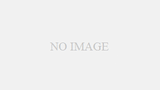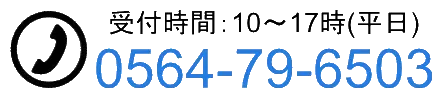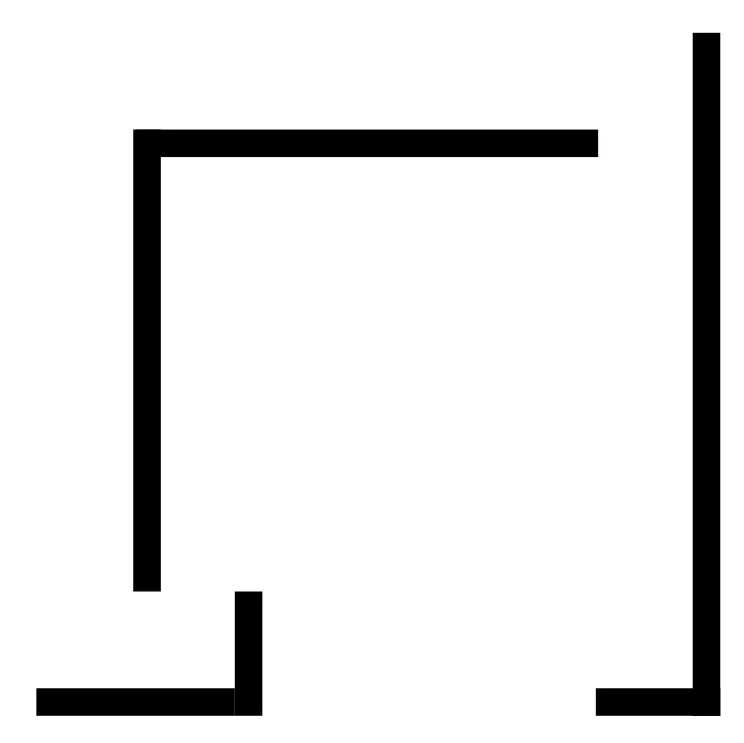-2.png)
「自分に合った働き方って何だろう…」
一人で悩んで、貴重な時間を無駄にしていませんか?
あなたの適性や希望に合わせた働き方のご相談まで、
障害福祉の専門スタッフがサポートします。
あなたが「納得して、次の一歩を踏み出すこと」です。
就労継続支援B型とは?をわかりやすく解説
「就労継続支援B型」という言葉、なんだか少し、硬い感じがしますよね。
でも、その本質はとてもシンプルで、温かいものなんです。
まずは、このサービスが私たち現場の人間にとって、そして利用者さんにとって、一体どのような場所なのか、心の壁をとかすように、ゆっくりとお話しさせてください。
- 就労継続支援B型は不安を抱える方の社会復帰を支える福祉サービス
- 厚生労働省の定義から見る就労継続支援B型の役割
就労継続支援B型は不安を抱える方の社会復帰を支える福祉サービス
この仕事を誰かに説明するとき、よくこんな風にお伝えしています。
「B型事業所は、社会復帰という空へ再び飛び立つための、心と体を慣らす優しい“滑走路”のような場所なんですよ」と。
障害や病気が理由で、いきなりフルタイムで働くことや、人間関係のプレッシャーが大きい職場に飛び込むのは、正直、怖いと感じるのが当たり前だと思うんです。
そんな方々が、例えば週に1日から、あるいは1日数時間の短い時間から、ご自身のペースで「働く」という感覚を、焦らず、少しずつ取り戻していく。
それがB型事業所の一番大切な役割だと考えています。大きな特徴は、事業所と「雇用契約を結ばない」こと。
だからこそ、「今日は少し体調が優れないから、午前中だけ頑張ろう」といった、その日の自分に正直な働き方ができるんですよね。
これって、再び社会へ踏み出すための、とても大切な“心の安全基地”になると思いませんか?
厚生労働省の定義から見る就労継続支援B型の役割
少しだけ、国が定めた公式な説明にも触れておきましょうか。
厚生労働省は、このサービスを「通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス」と定めています。
…うん、やっぱり、これだけ聞くと少し難しく感じますよね。
つまり、「色々な事情で、今すぐ会社で働くのは難しい。でも、何か役割を持ちたい、社会とつながっていたい。そんな切実な思いを抱えた方々が、作業を通して働く喜びを感じ、自信という名の栄養を蓄えるための場所」ということです。
お金を稼ぐこと“だけ”が、ここでの目的ではありません。
日中の安心できる居場所であり、社会との接点であり、そして何より、その人らしい生活のリズムを取り戻すための、大切なステップなのです。
就労継続支援B型はどんな人が利用できるの?対象者と利用条件
「うちの子(私)も、対象になるんだろうか?」
ご相談を受ける中で、この質問をされない日はありません。
これは、あなたやご家族の将来に関わる、大切な問いですよね。
- 身体障害・精神障害・知的障害・発達障害や難病のある方
- 年齢制限は基本なし!65歳以上でも利用可能
- 利用に障害者手帳は必須?医師の診断書や意見書でも相談可能
身体障害・精神障害・知的障害・発達障害や難病のある方
まず、知っておいてほしいのは、B型事業所は、障害の種類で利用できる方を区切ることはない、ということです。
身体障害や知的障害はもちろん、うつ病や統合失調症といった心の病気、ASDやADHDなどの発達障害、あるいは指定難病と向き合っている方など、本当に様々な方がいらっしゃいます。
大切なのは、障害の名前や診断名ではありません。
「一般の会社で働くには、少し配慮やサポートが必要だ」
「自分のペースで、できることから、もう一度始めてみたい」
という、ご本人の今の正直な気持ち。それだけなんです。
年齢制限は基本なし!65歳以上でも利用可能
「もう、いい歳だから…」なんて、思っていませんか?
B型事業所の利用に、年齢の上限は基本的にありません。(※18歳以上の方が対象です)
実際に、65歳を過ぎてから、「日中の活動の場として、社会とのつながりを持ち続けたい」という理由で、新しく利用を始められる方もたくさんいらっしゃいます。
若い方にとっては、社会に出るための“練習の場”として。
そして、年齢を重ねた方にとっては、地域での“新しい役割を見つける場”として。
人生の様々なステージに、B型事業所はそっと寄り添える場所なのです。
利用に障害者手帳は必須?医師の診断書や意見書でも相談可能
「障害者手帳がないと、福祉サービスは使えないのでは?」
これも、本当によくある誤解の一つなんです。
もちろん、障害者手帳をお持ちであれば、手続きはスムーズに進みます。
でも、手帳がないからといって、諦める必要はまったくありません。
医師の診断書や、定期的に通院していることを証明できるもの(自立支援医療受給者証など)があれば、お住まいの自治体の判断で、サービスの対象として認められるケースは本当にたくさんあります。
「自分はどうだろう?」と一人で悩む時間が、一番もったいないです。
まずはお近くの市区町村の窓口や相談支援事業所に、「ちょっと聞いてみたいんですけど」くらいの軽い気持ちで、気軽に問い合わせてみてくださいね。
受給者証を取得するまでの流れについては、「受給者証について」でご紹介しておりますため、ご覧ください。
-2.png)
「自分に合った働き方って何だろう…」
一人で悩んで、貴重な時間を無駄にしていませんか?
あなたの適性や希望に合わせた働き方のご相談まで、
障害福祉の専門スタッフがサポートします。
あなたが「納得して、次の一歩を踏み出すこと」です。
就労継続支援B型を利用するメリットとデメリットとは
どんなサービスにも、光の当たる面と、そうでない面があります。
ここでは、B型事業所を利用する上でのメリットとデメリットを、包み隠さずお伝えしますね。
あなたにとって、ベストな選択をするための、大切な判断材料にしてください。
- メリット1:自分のペースで無理なく通える
- メリット2:専門スタッフの手厚いサポートを受けられる
- メリット3:同じ境遇の仲間と出会える
- デメリット:工賃が低く経済的な自立は難しい
メリット1:自分のペースで無理なく通える
自分のペースで無理なく通えるは、やはり最大のメリットではないでしょうか。
「今日は頑張れそう」「今日は少し休みたい」その日の心と体の声に、正直になれる場所。
「行かなきゃいけない」というプレッシャーが少ないからこそ、「行ってみようかな」という前向きな気持ちが、自然と生まれやすくなります。
社会から長く離れていた方にとって、これ以上ないほど優しい第一歩になるはずです。
メリット2:専門スタッフの手厚いサポートを受けられる
仕事で分からないことがあった時。
作業中に、ふと気分が悪くなった時。
「大丈夫ですよ」と、すぐに駆けつけてくれる専門の職員が、いつもすぐ側にいる。この安心感は、何物にも代えがたいものがあります。
福祉のプロとして、そして、一人の人間として、あなたの挑戦を、一番近くで、ずっと支えます。
メリット3:同じ境遇の仲間と出会える
「自分のこの辛さは、きっと誰にも分かってもらえない…」
そんな風に、一人で孤独という名の分厚い壁に、心を閉ざしていませんか?
事業所には、あなたと同じように、見えない壁と向き合い、悩み、それでも前を向こうとしている仲間がいます。
何気ない会話の中から、「悩んでいるのは、自分だけじゃなかったんだ」と、心がふっと軽くなる瞬間が、きっとあるはずです。
B型事業所は、安心して自分らしくいられる“居場所”にもなるのです。
デメリット:工賃が低く経済的な自立は難しい
工賃が低く経済的な自立は難しいは、先ほども触れた、とても大切な点です。
やはり、B型事業所の工賃だけで、一人で生活していくことは、残念ながら、難しいのが現実です。
だからこそ、利用を考える際には、障害年金や、ご家族のサポートなど、他の収入と合わせて、生活全体のプランを一緒に考える必要があります。
この点は、契約を結ぶ前に、事業所の職員と、しっかりお話ししましょうね。
就労継続支援B型の具体的なサービス内容と仕事例
さて、ここからは「じゃあ、B型事業所では、毎日どんなことをするの?」という、より具体的なお話に入っていきましょう。
事業所での一日を、少しだけ覗いてみるような気持ちで、読み進めてみてください。
- どんな仕事をするの?事業所による多様な生産活動
- 1日のスケジュール例で見るB型事業所での過ごし方
- 仕事以外のサポート体制!職員の役割と相談できる悩み
どんな仕事をするの?事業所による多様な生産活動
B型事業所で行う仕事内容は、本当に多種多様で、まるで、個性豊かなお店がたくさん集まった市場のようです。
例えば…
- コツコツと、何かに没頭するのが得意な方には、雑貨の組み立てや、部品の検品。
- パソコンに興味がある方には、データ入力や、簡単なデザイン作業。
他にも、パンやお菓子を焼くいい匂いが漂ってくる事業所もあれば、土の匂いに癒されながら野菜を育てる農作業を行う事業所、地域のお店と連携して、ピカピカに磨き上げる清掃作業を請け負う事業所もあります。
大切なのは、「これなら、自分にもできるかも」「なんだか、楽しそう」と、あなた自身の心が、少しでも動くかどうか。
ぜひ、色々な事業所を見学して、あなたが「これだ!」と思えるような仕事内容を探してみてください。
1日のスケジュール例で見るB型事業所での過ごし方
事業所での一日は、どのようなリズムで進んでいくのでしょうか。
もちろん、事業所やその日の体調によっても変わりますが、
ここでは、ある一日の岡BASE ピーシーラボのケースをご紹介しますね。
- 10:00 来所・挨拶(みんなで顔を合わせ、心と体をほぐします)
- 11:00 小休憩(リフレッシュタイム)
- 11:10 作業再開(自分のペースで、作業に取り組みます)
- 12:00 昼食・休憩(栄養バランスの取れた昼食を食べます)
- 13:00 生産活動・創作活動(疲れたら、無理せず休憩も挟みます。それがB型です)
- 14:00 小休憩(リフレッシュタイム)
- 14:10 作業再開(自分のペースで、作業に取り組みます)
- 14:50 片づけ・清掃(みんなで協力して作業場を整えます)
- 15:00 挨拶・終了(一日お疲れさまでした)
多くの事業所では、作業の合間にきちんと休憩時間を設けたり、気分がすぐれない時に、そっと横になれる「静養室」を用意したりと、一人ひとりが無理なく過ごせるような工夫を、たくさん凝らしているんですよ。
仕事以外のサポート体制!職員の役割と相談できる悩み
私たちB型事業所の職員は、ただ仕事のやり方を教えるだけの“先生”ではありません。
利用者さん一人ひとりが、安心して自分らしい一歩を踏み出せるよう、様々な面からサポートする“パートナー”でありたいと、心から思っています。
例えば、定期的な面談を通して、
「本当は、どんなことに挑戦してみたい?」
「最近、何か困っていることはない?」
といった、あなたの心の奥にある声に、じっくりと耳を傾けます。
仕事のことだけでなく、
「お金の管理が苦手で、つい使いすぎちゃうんです…」
「家族との関係で、ちょっと悩んでいて…」
といった、生活全般の相談に乗ることも、私たちの大切な役割です。
私たちは、利用者さんの“一番身近な相談相手”でありたいと思っています。
どんな小さなことでも、一人で抱え込まずに、いつでも声をかけてくださいね。
就労継続支援B型の給料(工賃)はいくら?「儲かる」という噂は本当?
さて、お金の話。これは、本当に大切ですよね。
「B型で働くと、どのくらいもらえるの?」という疑問に、
ここでは、正直にお答えしたいと思います。
- 平均工賃は月額17,031円!工賃が低い理由とは
- 「給料」ではなく「工賃」であることの意味
- 工賃アップに向けた国の取り組みと事業所の努力
平均工賃は月額17,031円!工賃が低い理由とは
厚生労働省の調査(令和4年度)によると、B型事業所の全国平均工賃は、月額で17,031円でした。時間額にすると243円です。
この数字だけを見ると、「え、それだけ…?」と、がっかりしてしまうかもしれません。そのお気持ち、よく分かります。
工賃が、一般的なアルバイトのお給料などと比べて低いことには、ちゃんとした理由があるんです。
それは、B型が何よりも大切にしているのが、「生産性」や「効率」といった言葉よりも、「利用者さん一人ひとりの、その日の体調や心のペース」だからです。
無理なく働けることを最優先にしているため、どうしても生産活動に充てられる時間は限られてしまいます。
工賃の額は、その優しい理念の裏返しでもある、とご理解いただけると嬉しいです。
ちなみに、愛知県と岡崎市の工賃や作業内容を、「令和6年度就労継続支援B型事業所の平均工賃額一覧」を参考に、独自に整理しました。
愛知県平均工賃:25,609円
岡崎市平均工賃:23,766円
愛知県平均定員:19.7人
岡崎市平均定員:19.2人
ご興味がある方は、問い合わせよりご連絡ください。
作業内容・詳細-scaled.webp)
「給料」ではなく「工賃」であることの意味
B型で得られるお金は、労働の対価である「給料」とは、少し意味合いが異なります。
これは、事業所が生産活動で得た利益から、必要経費などを引いたものを、
利用者さんへ分配する「工賃」と呼ばれるものです。
経済的な自立を目指す、という側面ももちろんありますが、それ以上に、「自分の頑張りが、ちゃんと形になった証」という価値が、すごく大きいんです。
「今月は、これだけ頑張れたんだ」
その達成感が、次の一歩を踏み出すための、何よりの自信につながっていきます。
多くの皆さんは、障害年金などと組み合わせながら、この工賃を、ご自身の社会参加の証として、大切に受け取られています。
工賃アップに向けた国の取り組みと事業所の努力
もちろん、「工賃は、高いに越したことはない!」というのは、現場の職員も、同じ気持ちです。
実は、国も「工賃をもっと上げていきましょう」という目標を掲げていますし、私たちのような事業所も、工賃を上げるために、日々、本当に様々な努力をしています。
例えば、より価値の高いオリジナル商品を作って、色々な場所で販売したり、地域の会社から「ぜひ、あなたたちにお願いしたい」と、安定的にお仕事をいただいたり。
利用者さんのスキルアップをお手伝いして、より高い工賃につながる作業に挑戦できるよう、サポートすることも大切な仕事です。
皆で力を合わせて作った商品が、誰かの手に渡って喜ばれる。
その結果として、工賃が少しでも上がる。
それは、私たち職員にとっても、大きなやりがいと喜びになっているんですよ。
就労継続支援B型の利用開始までの流れを5ステップで解説
「少し、興味が湧いてきたかも…」もし、そう感じていただけたなら、本当に嬉しいです。
ここでは、実際に利用を開始するまでの道のりを、一緒に一歩ずつ、確認していきましょう。
- 市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ相談
- 事業所の見学・体験利用
- サービス等利用計画案の作成
- 受給者証の申請・交付
- 利用契約と利用開始
ステップ1:市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ相談
あなたのお住まいの市区町村の役所にある「障害福祉課(※名称は様々です)」や、「相談支援事業所」が、最初の相談窓口になります。
「就労継続支援B型というサービスに興味があるのですが…」この一言から始まります。
ステップ2:事業所の見学・体験利用
気になる事業所に連絡を取って、見学や体験利用を申し込むのが、このステップです。
- 事業所の雰囲気は、どんな感じかな?
- どんな人たちがいるんだろう?
- 仕事内容は、自分に合っているかな?
パンフレットだけでは分からない、その場所の“空気感”や“匂い”を、ぜひ、あなた自身の肌で感じてみてください。
ステップ3:サービス等利用計画案の作成
「この事業所、なんだかいいな」
そう思える場所が見つかったら、相談支援事業所の専門員の方と一緒に、「サービス等利用計画案」というものを作ります。
これは、「これから、どんな目標を持って、どんな風に過ごしていきたいか」をまとめる、あなたの未来のための、大切な“設計図”です。
あなたの「やってみたい」という気持ちを、どうか遠慮なく、たくさん伝えてくださいね。
ステップ4:受給者証の申請・交付
設計図ができたら、それを持って、再び市区町村の窓口へ行き、サービスの利用申請をします。
審査が無事に通ると、「受給者証」という、サービスを利用するための“パスポート”のようなものが、あなたのお家に届きます。
ステップ5:利用契約と利用開始
いよいよ最終ステップです。
利用したい事業所へ行き、正式な利用契約を結びます。
分からないことは、納得できるまで、何度でも質問してください。
契約が済めば、いよいよ、あなたの新しい日々のスタートです。
【比較表】就労継続支援B型とA型・就労移行支援との違いとは
B型について少しイメージが湧いてきたところで、今度は、よく似た名前の「A型」や「就労移行支援」との違いを見ていきましょう。
ここ、少しややこしいと感じる方が多いんですよね。大丈夫です、私がしっかり解説します。
この3つの違いが分かると、あなたにとって本当に必要なサービスがどれなのか、きっと見えてきますよ。
- 最大の違いは「雇用契約」の有無
- 目的や対象者も異なる!あなたに合うサービスを見つけよう
- 就労継続支援B型からA型や一般就労へのステップアップも目指せる
最大の違いは「雇用契約」の有無
就労継続支援B型と就労継続支援A型の違いを理解する上で、一番のキーワードは、何度かお伝えしている「雇用契約」です。
A型は、事業所と「雇用契約」を結びます。
これは、法律上の「労働者」になる、ということ。
だから、お給料には最低賃金が保証されます。
その分、「週〇日、〇時間以上」といった勤務のルールがあり、より一般の会社に近い働き方になります。
一方、B型は「雇用契約」を結びません。
だからこそ、体調に合わせてお休みしたり、通所時間を調整したりといった、
その日の自分を大切にする働き方ができるんです。
もらえるお金は「給料」ではなく、「工賃」と呼ばれます。
プレッシャーの中で働くのは、まだ少し怖い。そう感じる方にとって、この「雇用契約がない」という事実は、本当に大きな安心材料になることが多いんですよね。
なので、B型事業所に通所することで「お仕事をしています」と言えて、自信の積み重ねにも繋がります。
目的や対象者も異なる!あなたに合うサービスを見つけよう
A型、B型、そしてもう一つの「就労移行支援」。
これらは、目指すゴールがそれぞれ違います。
どのサービスが合っているかは、あなたの「今」の気持ち次第です。
- 就労移行支援:ゴールはズバリ、「一般企業へ就職すること」。ビジネスマナーやPCスキルなどを学び、就職活動のサポートを受ける場所です。言うなれば、「就職のための、大人の学校」のようなイメージでしょうか。原則2年という利用期間があります。
- 就労継続支援A型:ゴールは、「支援を受けながら、安定して働くこと」。すぐに一般企業で働くのは少し不安だけど、雇用契約のもとで責任を持って働きたい、という方向けです。
- 就労継続支援B型:ゴールは、「自分のペースで、働くことに慣れること」。まずは生活リズムを整えたい、日中の居場所がほしい、という方が、無理なく社会参加を目指すための場所です。
どのサービスが良いとか悪いとか、そういう話では全くないんです。
あなたにとって「今、一番しっくりくる場所」を選ぶことが、何よりも大切なんですよ。
もっと、就労継続支援A型とB型の違いを知りたい方は、「就労継続支援A型B型の違いがわからない方向け!給料や仕事内容を比較してどちらが向いているか判断できるポイントを解説」をご覧ください。
就労継続支援B型からA型や一般就労へのステップアップも目指せる
B型事業所は、決して“終着点”ではない、ということです。
むしろ、未来へ向けた“出発点”や“準備ステーション”だと、考えています。
B型で働くことに慣れ、
「もう少し、働ける時間や日数を増やせるかも」
「新しい仕事に挑戦してみたい!」
といった自信の芽が、心の中にぽっと灯ったら、
A型事業所や一般企業への就職へと、ステップアップしていく道も、もちろんあります。
多くの事業所では、利用者さんのそんな前向きな気持ちを全力で応援します。
「次へ進みたい」と感じたときには、いつでも相談してくださいね。
一緒に、未来への作戦会議をしましょう。
就労継続支援B型とはに関するよくある質問
最後に、よくいただく質問とその答えを、Q&A形式でまとめてみました。
- Q:就労継続支援B型はどんな人が対象ですか?
- Q:就労支援A型とB型の違いは何ですか?
- Q:就労継続支援B型は誰でも入れますか?
- Q:B型作業所で働くと月いくらもらえますか?
Q:就労継続支援B型はどんな人が対象ですか?
A:障害や病気があって、今すぐ一般の会社で働くのは少し難しい、と感じている方なら、どなたでも対象になる可能性がありますよ。
例えば、「一度就職したけれど、人間関係で心が疲れてしまった方」「長い間、お家から出られずにいた方」「自分のペースで、できることからもう一度始めたい方」など、本当に様々な方が利用されています。
Q:就労支援A型とB型の違いは何ですか?
A:一番の違いは、「雇用契約を結ぶかどうか」です。
A型は雇用契約を結んでお給料をもらう、より“働く”に近い形。B型は雇用契約を結ばず、自分のペースを大切にしながら「工賃」をもらう、“訓練”や“居場所”に近い形、とイメージしていただくと、一番分かりやすいかと思います。
Q:就労継続支援B型は誰でも入れますか?
A:いいえ、残念ながら誰でもすぐに、というわけではないんです。
お住まいの市区町村に申請をして、「障害福祉サービス受給者証」という許可証を発行してもらう必要があります。
でも、先ほどお話ししたように、手帳がなくても利用できる可能性は十分にありますので、「自分は無理かも」と決めつけずに、まずは相談してみてくださいね。
Q:B型作業所で働くと月いくらもらえますか?
A:これは、通う日数や時間、そして事業所の仕事内容によって本当に人それぞれなんです。
全国平均では月額17,000円ほどですが、もっと高い方もいらっしゃれば、低い方もいます。
ただ、これだけで生活を成り立たせるのは難しい、ということは、どうか心に留めておいていただけると幸いです。
まとめ:就労継続支援B型とは新たな一歩を安心して踏み出せる場所
就労継続支援B型とは、障害や病によって、社会から少しだけ距離ができてしまった方が、
もう一度、自分らしいペースで、社会とのつながりを取り戻すための、温かくて、優しい“リスタートの場所”だと、私は心から思っています。
そこは、ただ作業をするだけの場所ではありません。
朝起きて、「行く場所がある」と思えること。
誰かに、「ありがとう」と言ってもらえること。
他愛のないおしゃべりができる仲間がいること。
困った時に、「どうしたの?」と、優しく声をかけてくれる職員がいること。
そんな、日々の小さな喜びを、一つひとつ、大切に拾い集めていける“居場所”でもあるのです。
ぜひ一度、お近くのB型事業所の扉を、そっとノックしてみてください。
もしかしたら今、あなたの心の中には、ほんの少しの希望や、あるいはまだ拭いきれない不安が、渦巻いているかもしれませんね。
もし、あなたが愛知県岡崎市、またはそのお近くにお住まいでしたら、一度、私たちが運営する就労継続支援B型事業所「岡BASE ピーシーラボ」に、見学・体験にいらっしゃいませんか。
この記事でお伝えしてきた「自分のペースで、安心して通える居場所」を、岡崎で、心を込めて作っています。
私たちの理念は、「あなたの『やりたい』で、未来をひらく」こと。
「体験」といっても、難しいことは何もしません。
まずは、事業所の温かい雰囲気を感じて、お茶を飲みながら、
スタッフと少しお話ししてみる。
それだけでも、心の中の景色が、少し変わるかもしれません。
「ここなら、大丈夫かも」
その小さな安心感を、持ち帰っていただくことが、何よりの願いです。
もちろん、見学したからといって、利用を無理強いすることは絶対にありません。
ご本人だけで来るのが不安なら、ご家族と一緒にお越しいただくのも大歓迎です。
“今の毎日”から抜け出すきっかけは、ほんの少しの勇気と、小さな行動から生まれます。
「ちょっと、話を聞いてみたい」
そう思ってくださったなら、下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
お電話でも、もちろん大丈夫です。
ご連絡を、スタッフ一同、心からお待ちしています。
電話番号:0564-79-6503